経歴
1995年(平成7年)3月に県立川越南高校を卒業。1998年(平成10年)3月には日本鍼灸理療専門学校(花田学園)を卒業し、同年、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の国家資格を取得。その後、経絡治療を実践する横浜市の本田鍼灸院にて研鑽を積み、2001年(平成13年)4月より地元埼玉県日高市にて往診専門の鍼灸専門での施術を開始。2002年(平成14年)2月には、同地域に松本鍼灸院を開院し、地域医療に貢献している。患者の多くは紹介によるもので、比較的広い商圏から訪れる患者を受け入れ、地域医療の一端を担う存在として信頼を集めている。
2008年(平成20年)7月には株式会社プロレイアップを設立し、法人化を果たす。これにより、経営基盤を強化するとともに、スタッフの育成や研修に積極的に取り組む体制を整える。患者一人ひとりに寄り添う丁寧な施術を信条とし、未病治や虚弱、疲労感といった一見すると理解されにくい症状の改善を得意分野としている。年間のべ5000人に及ぶ患者の診療に携わり、多くの期待に応えるべく奮闘している。
また、鍼灸の根源である東洋医学の思想を深く理解し、その実践を通じて社会とのつながりを重視している。その一環として、地域社会への貢献活動にも力を入れ、講演会の開催や地元ロータリークラブ、民間の勉強会などで講師依頼があり講演を務める機会も多い。これらの活動では、鍼灸や東洋医学の魅力を広く伝え、多くの参加者から好評を博している。日々研鑽を重ね、技術と知識の向上を追求しながら、患者と地域社会に貢献を旨に仕事を続けている。
2025年(令和7年)4月からは、念願の鍼灸師・鍼灸学生向けコンサルティング事業を開始。新人鍼灸師の育成や経営改善のアドバイスを行い、業界全体の発展にも寄与すべく発信していく。
鍼灸について
鍼灸学生のころ、早くから鍼灸で身を立てるのは無理だという話しを聞いており、成りたくてなろうとしている青年の出鼻をくじいたのをよく覚えている。1年の秋から経絡治療の勉強会に参加し、また書籍によって脈診に興味を持ち、古典(素問や霊枢)の存在を知るにつけ、本来の伝承されてきたであろう東洋医学に興味を持つ。
経絡治療の勉強会に参加する縁から勉強会の本部役員の先生のもとに3年間の修行を受け経絡治療の実際を知ることとなる。修行を終えて実家にて往診専門で開業。その頃は訪問鍼灸など今の高齢者向けのチーム医療などなく、個人営業の伝統鍼灸としてご理解いただきご紹介を受け仕事の数を増やしていった。同年の秋には1日で8軒ほどと移動するのに困難をきたすようになり、店舗を構えることを決意。翌年2月に鍼灸院開院となる。
開院後は往診時とはまったく違い時間に余裕ができる。幅広い勉強の必要性を感じるが、鍼灸のスタイルとしては10年やり通せという先輩の言葉を信じて、ある意味、妄信的に経絡治療の精度を高めることに邁進していった。開業数年後にスタッフの助けを借りるようにし、またさらに数年後に法人成りをして事業的基盤を盤石なものにする。当初からいわゆる集客に困ったことは無いが、そのターニングポイントはただひとつ。宣伝よりも目の前の患者さんに自分の全力を注ぐこと、と開き直れたからだと振り返る。
開業後、15年を過ぎた頃からさらなる視野を広げようと他流派をみつつ、ある先生を知る。その先生とは年代は近く長い付き合いとなるであろうと喜んでいたが、急逝され自分の使命を再考するようになる。この出来事がその後、流派を超えて卓越性を求める旅の始まりとなる。あわせて定期的に発せられる「鍼灸師食えない問題」に一応の答えを出し、終止符をつけるためにコンサルティグを通じて積極的に求めに応じて助言することを決意する。
背景について
私淑している人物を以下に挙げ私という人物の理解にお役立ていただきたい。
安岡正篤
安岡正篤(やすおか まさひろ、1898年2月13日 – 1983年12月13日)は、日本の陽明学者であり、思想家、教育者である。奈良県に生まれ、早稲田大学卒業後、陽明学を中心に東洋思想の研究と実践に取り組んだ。「知行合一」を重視し、人格形成や社会調和を目指す教育活動を展開。1932年に「金鶏学院」を設立し、戦後は政治家や経済人を指導、「昭和の指南役」として知られた。また、『易経』にも精通し、東洋思想を基盤とした人生哲学を説いた。著書に『運命を拓く』『人物を修める』などがあり、その思想は時代を超えて日本人の精神的指針として受け継がれている。
安岡先生の儒学、陽明学、そして易の思想に強く影響を受けた。地元近くの嵐山で行われた勉強会にも参加できる機会があれば足を運び、東洋思想の研鑽に努めた。書籍を通じて自己を確立することの重要性を学び、その教えは鍼灸施術のみならず生き方にも大きな影響を与えている。先生を通じた古典の再考はいくら時間があっても足りないが、指し示す方向を確固たるものにしてくれた大きな存在である。
澤瀉久敬
澤瀉久敬(おもだか ひさゆき、1904年4月3日 – 1995年1月23日)は、日本の医師、医学者、思想家であり、東洋医学と西洋医学の融合を目指した人物である。東京帝国大学医学部を卒業後、精神科医として活動し、精神医学や心理学の研究に取り組んだ。東洋思想や仏教哲学にも深く傾倒し、それを医療や人間理解に応用する独自の思想体系を構築した。特に「身心一如」の考え方を重視し、心と体の調和を説いた。著書には『心身医学』や『人間学としての医学』があり、医学を超えた広範な人間学的視点を提示した。澤瀉の思想は、現代においても医療や哲学の分野で高く評価されている。
澤瀉先生は医学部でも教鞭をとり、哲学的視点から医学の考え方を説かれた。西洋医学に限らず医学のあるべき姿として東洋医学の優位性を見出し、鍼灸師に方向性と希望を指し示した。単純に西洋医学と東洋医学をいっしょにやればいいとか治ればいいという安直な発想に警告をあたえ、哲学から派生して生命論や科学論まで貴重な視点と提言を与えてくれる。厳しくも真実を告げる見解は鍼灸師にとっても希望となるものである。
瀧本哲史
瀧本哲史(たきもと てつふみ、1972年10月 – 2019年8月10日)は、日本の投資家、経営コンサルタント、教育者であり、多方面で活躍した人物である。京都大学法学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。その後、エンジェル投資家としてベンチャー企業の支援に携わりながら、教育分野にも注力した。京都大学で講義を行い、若者に「自ら考え行動する力」を説き、未来を切り開く重要性を訴えた。著書『僕は君たちに武器を配りたい』はベストセラーとなり、思考力や行動力の重要性を多くの読者に伝えた。生涯を通じて、次世代の育成と社会の変革に尽力した人物である。
瀧本先生はビジネス的視点と社会貢献、そして自己実現のあり方などを示してくれた。本当に惜しまれることに急逝してしまい佳人薄命という言葉を印象付けた方だ。後進の育成を強く考えるようになったのも先生の視点があってこそ。とかく鍼灸・東洋医学とは違うような、いわゆる科学的見地のように感じるが実際は東洋医学はそこまでナラティブではなく、ロジカルで通じる点が多いことに気付か学びが多い理由でもある。もちろん、それは瀧本先生の指摘にあるものではなく私がそのように理解するもので結果を出していく再現性には、これくらいロジカルで進めなければならない証左でもあると痛感している。
田坂広志
田坂広志(たさか ひろし、1951年9月 – )は、日本の思想家、実践家、教育者であり、多分野で活躍する人物である。東京大学大学院工学系研究科を修了後、米国タフツ大学フレッチャー法律外交大学院で国際政治経済学を学び、博士号を取得。その後、多摩大学大学院教授やシンクタンク・ソフィアバンクの設立を通じて、社会変革やリーダーシップの研究・実践に取り組む。特に「見えない資本」や「志の経営」などの概念を提唱し、企業経営や個人の生き方に深い影響を与えている。著書には『風の時代の生き方』『仕事の思想』などがあり、幅広い層に支持されている。
田坂先生は東洋思想を言わずとも東洋思想を授けてくれる。田坂先生も東洋医学、東洋思想を前面に出しているわけではないが、その所作・発想はかなり東洋思想と言ってもよいように感じる。抽象的な事柄から一般的に流される視点に優しい口調ながら警告を与え、穏やかな情緒ながら畏怖の念を抱くのも正直なところである。目下、私淑する先生方のなかで唯一ご存命だということもあり、まだまだ学びを乞うことができる喜びと少しでも理解し実践しなければというはやる気持ちを感じさせる方である。
資格について
本業に関わる資格は、はり師きゅう師あん摩マッサージ指圧師を第5回の国家資格で取得。実際には鍼灸専門で開業しているので、あん摩マッサージ指圧師の資格はあるけれど、技能的には使う機会がない。いわゆる流派としては古典派、経絡治療の専攻ではあるが、奇経治療などを重層的に取り入れている。
ある程度、キャリアを積んでいくと鍼灸師や鍼灸学生からの相談も当然のように増えていく。なかでも金銭的な課題に繋がる内容が多く、その解決にはライフプランニングの崩壊を防ぐ(そもそもライフプランニングで意思とキャッシュフローがちぐはぐが原因だというケースが多い)ことが先決だと考え、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。あわせて資産形成コンサルタント、B/S P/L検定2級などを取得し、ライフプランニング(なかでも資産形成と事業の財務諸表)に助言できる視野を確保。鍼灸院経営の実務に限らず、個人のライフプランニングと調和のとれた助言を可能にした。
2025年は事業へのアドバイスも可能にすべくさらに周辺資格の取得も検討中。
コンサルティグについて
東洋医学である鍼灸はその根源を人間学・運命学という実学に置き、いうなれば役に立つ学問ということになる。患者を治すのも、鍼灸師が増えればその確率が高くなり、素晴らしい鍼灸師が増えれば、さらにその確率が高くなるのは自明である。しかしながら、現実は食うに困る鍼灸師か暇やゆとりを誇る鍼灸師、はたまたセルフブラック化や勉強会での上納という構図に生きるラットレースというものまで様々である。
それらを打破するには、鍼灸もしくは鍼灸師、鍼灸院のコンサルティグが必要と考えるが、それぞれ意味することは少しずつ違う。鍼灸のコンサルというより鍼灸師のライフプランニングを含めたコンサルティグというのが一番、東洋医学的問題解決に近いであろう。それは何をするのではなく、誰がするのかという人が中心にあるからである。東洋思想の根底はどこまでいっても人が不在になることはない。技術、テクニックで完結することではないのである。そのため鍼灸を通じて患者、ひいては社会をよくしようという同志のために、助力・助言できることが重要であり、それは何も言う側(私)だけの努力で成立するものではない。聞いて理解する側(クライアント鍼灸師)にも多分に自覚と覚悟が求められることになる。だからこそ、簡単に売上や収入があがるという欲を煽る言い方ではなく、社会貢献が大前提で、文字通りお金は後からついてくるという形で、貢献の実績を実感することになるだろう。小手先の集客、営業、金儲けとは一線を画すことになるが、鍼灸コンサルと言った瞬間、(既存の悪徳コンサルを含め)厄介者と同一視されるであろうが、わかる人にはわかるという経験は鍼灸の実業においても同じ印象をもっているのでいまさら驚かない。期間は最低2年とし、その後は継続するか不明だが、それまではきっちり必要の声に応じて活動していくつもりである。
使命について
自身の半生についてはかなり長くなるので大幅に割愛するが、鍼灸師になりたくてなったのは間違いない。サラリーマンになりたくないではなく、サラリーマンになれないであろうと冷めた幼少期を過ごす。その理由は幼少期から虚弱で頭痛や蓄膿症をずっと患い、そのため病院通いが常であったからだ。鍼灸によって健康を取り戻し、中学生の頃には鍼灸師になることを意識して過ごす。高校では当時の鍼灸専門学校が狭き門ということを知っており、受験前々年、前年、その年の入学願書を取り寄せ、願書に付属している入試問題の研究をしていた。
開業後数年は、小さい子どもも数多く来院し、報恩の意味を実感しながら臨床を過ごす。近隣のクリニックからも患者を紹介されるようになり、さらなる使命感を得て東洋医学の真髄を身につけるべく仕事に情熱を傾ける。
一日で診きれない患者があることをストレスに感じつつ、同時に後進の育成を意識し始める。易経の勉強がてらここ5,6年ほど必ず年筮(来年の運勢の占いを立てること)を行い、そこから卓越した先生と出会ったり、資格取得の勉強を始めたり、自らの道しるべとして経学と易経を中心に据えるようになる。東洋医学、東洋思想といいながら、そのような本道を歩む先輩が少ないことに悩みを感じ、仕事で結果を出すことも大切だが、後進を育成することも大切と考えるようになる。自分だけで終えられる内容ではなくなっており、同時に同志を求めつつ、少しでも東洋医学の本質に迫られるように、また社会的な財産を後世に残すべく、それらを使命と感じ、行けるところまで行ってみようと覚悟したところである。

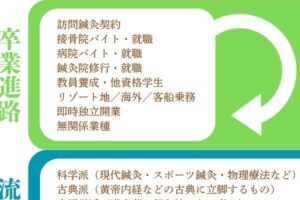
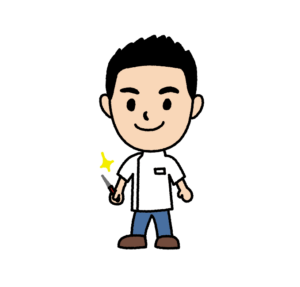
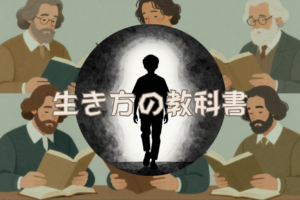


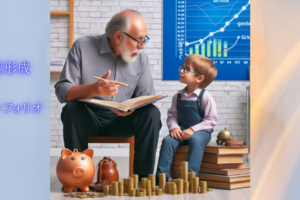
コメントを残す